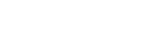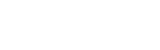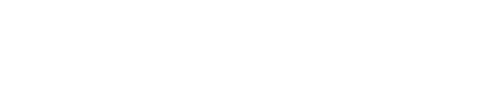お香の歴史

信仰の香りから暮らしの楽しみへ。
いつの時代も、人々のそばには香りがありました。
日本におけるお香の歴史をたどります。
~飛鳥時代

538年(552年の説も) 仏教伝来
日本で「香」が用いられるようになったのは、仏教伝来の頃と考えられています。
さまざまな仏教儀礼とともに香もまた、大陸から伝えられました。
595年 日本で最も古いお香の記述
『日本書紀』には「ひと抱えもある大きな沈水香木が淡路島に漂着し、島人がそれと知らずかまどに入れて薪とともに燃やしたところ、その煙が遠くまで薫り、これを不思議なこととしてこの木を朝廷に献上した」と記されています。
~奈良時代

当時は、主に仏前を浄め、邪気を払う「供香(くこう・そなえこう)」として用いられ、宗教的な意味合いが強いものでした。
香料は、直接火にくべてたかれていたと考えられます。
鑑真和上来日
鑑真は仏教の戒律と共にたくさんの香薬を日本にもたらし、また香の配合技術も伝えたと言われています。唐様の教養としてそれらを学んだ貴族たちは、仏のための供香だけでなく、日常生活の中でも香りを楽しむようになりました。
~平安時代

香料を複雑に練り合わせ、香気を楽しむ「薫物」が貴族の生活の中で使われるようになります。貴族たちは自ら調合した薫物を炭火でくゆらせ、部屋や衣服への「移香」を楽しみました。
平安時代の王朝文学には、香の記述が多く見られ『枕草子』や『源氏物語』にも散見されます。
~鎌倉・室町時代

武士が台頭し、禅宗が広まった鎌倉時代は、香木そのものと向き合い、一木の香りをきわめようとする精神性が尊ばれるようになります。この頃に、香木の香りを繊細に鑑賞する「聞香」の方法が確立されました。
そして、室町時代に東山文化が花開いていく中、茶の湯や立花と同じく香も、寄合の文化の一翼を担っていきます。
~江戸時代

貴族、武士階級の他に経済力をもった町人にも香文化が広まります。
「組香」の創作や、それを楽しむために多くの優れた香道具が作られました。香を鑑賞するための種々の作法が整えられ、香は「道」として確立されていきます。
一方、中国からお線香の製造技術が伝わり、庶民のあいだにもお線香の使用が浸透していきます。
現代

時代の変遷にともない、薫香業界も、現代の日本人の暮らしにあった新しい香りの開発をたゆむことなく続け、さらに新しい歴史を刻もうとしています。