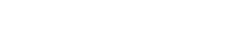- 旅の記憶
- 光る君に至るまで
- 表意と表音
- 志野宗信公五百年忌
- 香りってなに
- 中田浩二さんを悼む
- 寄り合うこと
- 蒼い香りと「令和」
- 30年という歳月
- 嗅覚と笑い
- 移り香
- 30年を迎えて
- 姉妹都市交流55周年 ボストンでコンチキチン
- 久蔵不朽 −久しく蔵して朽ちず−
- 異界と「丹の国」と
- SNS、五感、そして香り
- 生物多様性に生きる
- 匂いの発見
- 源氏千年紀に
- 祇園精舎での一会
- 宝船
- 背中に感じる巨大な息遣い
- らすとサムライ
- 伝統と革新の関係、その付き合い方
- データベースのすすめ
- 王朝の美学...消去法
- 3650
- 心清聞妙香
- 真新人類、待望論
- 香り...時空を越えて
- 香り...メディア??
- 君は船に乗るのか?
- Leotard
- 歴史のフィルター
- Huさん
- 常夏の街で
- 自然と芸術
- 赤いヤッケとリゾート開発
志野宗信公五百年忌
志野宗信公五百年忌に寄せて/令和5年4月
聞香の道を大成したという志野宗信は、大永3年(1523)に亡くなったという。今年はそれから500年。遠忌を記念して香道志野流の蜂谷家によって東山慈照寺で法要が勤められた。また京都岡崎の細見美術館では、「香道志野流の道統」という特別展が催されている。弊社の薫習館ギャラリーでも、「聞香の系譜 志野宗信公五百年忌に寄せて」と題して関連の特別展示を実施した。
そもそも「聞香」は、いつの時代にどのように始まったのだろうか。詳細はあまり明らかではない。宋や明の時代に「隔火」と呼び火力を弱める知恵があったことに、我が国の「聞香」文化は大きなヒントを得ていたのであろう。1334年の二条河原の落書に、鎌倉でも行われていたがとして「茶香十炷の寄合」が近頃都で流行ると記録を残している。この十炷の寄合を行うには、聞香は欠かせなかったであろう。14世紀には、婆娑羅大名として名を馳せた佐々木道誉の香木の蒐集が歴史に知られる。15世紀にかけて、北山文化、嘉吉の乱などを経て、混沌とした社会は、ついに11年に及ぶ応仁の乱を引き起こし、都を戦さ場にし灰燼に帰してしまった。多くの人びとが地方へ避難し、人びとは命のどん底を目の当たりにすることとなった。それが結果的には、精神性の高い審美眼を養い、また自然の営みの絶対性を哲学の根本として、今日の世界にも強く影響力を持つ日本文化の息吹を呼び覚ますこととなった。
このような時代背景の中で、聞香も喫茶や連歌・立花などと共に寄合の手立ての一つとして人々の心の襞を慰める一助となった。戦乱の世の中は、瀬戸内の安全を奪い、土佐沖を利用する外海航路の発展に繋がった。そのことが大和川の河口に町の形成を進め、堺の出現と発展を促すこととなった。海洋国家として尚氏琉球王朝の活躍も新しい時代の発展に大きく寄与している。
14世紀から15世紀にかけて、香は茶と共に武家文化の一画を彩る芸道文化として発展している。ただこの二つには大きな条件的な相違点があった。茶は、国内で毎年収穫できる日常性を得る一方、香は、舶載されてくる限られた供給に対する希少性を念頭に置いておかないとその恩恵を享受することは許されない。繊細に関わることによって、天然の香木が一つ一つその個性を持ち合わせていることに気付き数多くの木が蒐集された。佐々木道誉の香木が義政に引き継がれ、それを宗信が鑑定分類したという。毎年の収穫の品質を楽しみに吟味する茶の楽しさとは裏腹に、天然の香木を極小片に切り取り柔らかく加熱することで醸し出される香気に集中する楽しさ。そして貴重な香木を次世代に引き継ぐ意識。日常を非日常としてかけがえのない一碗と考える茶と、非日常の小片を日常の気分で楽しむ香。二つの芸道文化が同じ社会環境の中で、寄合の手立てとして発展していく道は、全く相反する道だった。しかしその目指す頂は寄り合うことによって確信することのできる命の一期だったのだ。
志野宗信公五百年忌に立ち会って、先達の知恵に感謝を覚えている。
筆者
畑 正高(香老舗 松栄堂 前社長)
前社長が千年の都に生まれ育ち、薫香という伝統文化を生業にして、日頃考えることや学んだことを折に触れ書きつづったコラムです。