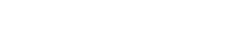- 旅の記憶
- 光る君に至るまで
- 表意と表音
- 志野宗信公五百年忌
- 香りってなに
- 中田浩二さんを悼む
- 寄り合うこと
- 蒼い香りと「令和」
- 30年という歳月
- 嗅覚と笑い
- 移り香
- 30年を迎えて
- 姉妹都市交流55周年 ボストンでコンチキチン
- 久蔵不朽 −久しく蔵して朽ちず−
- 異界と「丹の国」と
- SNS、五感、そして香り
- 生物多様性に生きる
- 匂いの発見
- 源氏千年紀に
- 祇園精舎での一会
- 宝船
- 背中に感じる巨大な息遣い
- らすとサムライ
- 伝統と革新の関係、その付き合い方
- データベースのすすめ
- 王朝の美学...消去法
- 3650
- 心清聞妙香
- 真新人類、待望論
- 香り...時空を越えて
- 香り...メディア??
- 君は船に乗るのか?
- Leotard
- 歴史のフィルター
- Huさん
- 常夏の街で
- 自然と芸術
- 赤いヤッケとリゾート開発
蒼い香りと「令和」
「かおり風景」第34回掲載/令和元年
国道162号線を北上する。市街地を離れるとすぐに新緑に満ちた山並みが迫ってくる。御経坂の小ぶりな峠を越えると視界が開け、三尾と呼ばれる紅葉の名所は四季を通じて美しい。愛宕山を前にして清滝川の谷が深い。渓流に沿って北上する。バイパストンネルのおかげで杉の銘木で知られる山城中川の里に気付くことなく道は続く。杉坂との別れを過ぎて、谷間にひらけた里は小野郷。世代を重ねた佇まいを残す林業家の屋敷を見ながら笠トンネルに入る。この辺りの金木犀が秋を告げると、母はいつも「松茸(まつたけ)が忙しくなる」と楽しみにしていた。笠トンネルで一段と坂を登り、細野の里に入る。この笠峠は分水嶺で、細野から上桂川水系に入る。峠を隔てて水系が変わるということは、古くからの生活文化圏が違い土地の人たちの帰属意識も変わる。ここから北桑(ほくそう)あるいは京北(けいほく)という地だ。この細野の里は裏愛宕の入り口でもあり、滝又の滝でも知られている。山が険しい中川や小野に比べて土地の標高が高い分だけ山が近く、里の雰囲気が穏やかなのが不思議だ。細野から北上する道は新しくできた栗尾トンネルを抜けて一気に周山の町に入る。栗尾峠も大きな峠だ。この峠から、長閑な周山の町や遠く若狭に続く街道の遠景が一望できたのだが、利便性のおかげで楽しむ機会を失ったことが少々残念だ。
周山にはこの地域の街道があつまり、穏やかな山々に囲まれた盆地もかなり広く、この町は森林資源の集散地として発展してきた。戦国時代の城跡も知られ、維新勤皇隊で有名な山国の里もここから東に入る。私はいつもこのまま若狭方面へ北上を続け、弓削上中を目指す。
母は、この山里の林業家の家に男女3人ずつ6人姉弟の長女として生まれた。母の祖父が郵便局長を引き受け、家の屋敷地の中に郵便局があり電話交換台もあった。大正15年生まれなので、多感な女学生時代は暗い戦争時代を過ごした。京都府立第二高等女学校(現在の朱雀高校)に学ぶ間、市内の叔母の家に世話になり、壬生から二条城まで通学したという。壬生寺へ節分のお参りに行くと必ず南東へ向かって散策を楽しんだ。すっかり変わっていても町並みが懐かしいらしい。前述のような大きな峠をゴトゴトとバスに揺られていくつも越えて、文化圏の違う京の街へ今の中学生ほどの女の子が一人出向く。人の身体力も精神力も今とは違ったとはいえ、心細いことであったろうと慮ってみる。京北の田舎では、昭和30年代までJRバスは「省線」と呼んでいた。それが「国鉄バス」になったのはいつ頃だったんだろう。終戦の頃、母は、周山の林務局に勤めていた。戦後の昭和23年に中京の商家に嫁いで父と一緒に力を合わせひたすら家業に励み、二人の子を育ててくれた。数え切れない苦労を重ねて、昭和から平成へと家業を守り盛り立ててくれた。
私が大学に入った頃から、母と一緒に京北の山に入る機会がしばしばあった。主に秋の松茸狩。世に言う楽しい行楽ではない。9月20日くらいから10月末頃まで、責任を持って山を管理しなければならない。山から一シーズンに何本の松茸を出すかは、神のみぞ知る事。それをいかに収穫するかは、管理者の醍醐味だ。経験と知恵がモノをいう。親指大も一本。大きな笠も一本。虫に喰われても一本。鹿に喰われも一本。人に盗まれても一本。収穫物はほとんどが進物となって他所へ貰われていった。春の蕨摘みも楽しかった。山菜は、どの山へ入っても構わない。日当たりの良い絶好の場所に踏み入ると、次から次へと蕨が目に入ってくる。両の手で摘みながら滑り落ちないように足を踏ん張ってどんどん我を忘れてしまうと、とんでもない急な斜面の高いところにいる自分に驚いてしまう。秋も春も、急坂を降りる時は収穫物を傷めないように気遣いが大変だった。夏の川では鮎が獲れる。柿や栗も楽しいのだが、「里の豊作、山不作」と言って松茸の方を祈ってきた。
5月の連休になると、毎年、若い人たちと蕨摘みに出かける。ワイワイとみんなで山に分け入ると、たくさんの蕨が瞬く間に収穫できる。今年は、台風の風で大きな痛手を被った山の姿が痛々しかったが、新緑の渓谷に鳥の歌声が響き、萌え出づる大地の緑は変わらない。蕨摘みに疲れ腰を伸ばすのに一息ついて谷間を見下ろす時、よごれた指先がふと蒼く香った。ひたすら蕨を追いかけていた自分がおかしい。仲間とも離れ一人風の音に包まれている。台風に見舞われても自然の営みは何も変わっていない。年老いた母を病室に残し、教えられたまま山に分入っている自分がいる。それなりにすっかり歳を重ねた自分がいる。
「令和」の時代を迎える。山の営みは何も変わっていなかった。蕨摘みの後の昼ごはんは、バーベキューが待っていた。今年は子供連れが多く、賑やかさが今までとまた違う。母のしていたように蕨を山と積み直し、長さを揃えながら束を作る。一人二人と集まってきて、子供たちに負けない賑やかさで作業場が大きくなった。母が作ったような綺麗な束はできないけれど、見よう見まねでそれらしいお土産の山となった。またあの蒼い香りが、ふと過った。
筆者
畑 正高(香老舗 松栄堂 前社長)
前社長が千年の都に生まれ育ち、薫香という伝統文化を生業にして、日頃考えることや学んだことを折に触れ書きつづったコラムです。