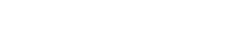- 旅の記憶
- 光る君に至るまで
- 表意と表音
- 志野宗信公五百年忌
- 香りってなに
- 中田浩二さんを悼む
- 寄り合うこと
- 蒼い香りと「令和」
- 30年という歳月
- 嗅覚と笑い
- 移り香
- 30年を迎えて
- 姉妹都市交流55周年 ボストンでコンチキチン
- 久蔵不朽 −久しく蔵して朽ちず−
- 異界と「丹の国」と
- SNS、五感、そして香り
- 生物多様性に生きる
- 匂いの発見
- 源氏千年紀に
- 祇園精舎での一会
- 宝船
- 背中に感じる巨大な息遣い
- らすとサムライ
- 伝統と革新の関係、その付き合い方
- データベースのすすめ
- 王朝の美学...消去法
- 3650
- 心清聞妙香
- 真新人類、待望論
- 香り...時空を越えて
- 香り...メディア??
- 君は船に乗るのか?
- Leotard
- 歴史のフィルター
- Huさん
- 常夏の街で
- 自然と芸術
- 赤いヤッケとリゾート開発
光る君に至るまで
「かおり風景」第39回掲載/令和6年
かねてから、多くのことを歴史に学んできた。楽しくて仕方がない。物事には、その背景があり、必然があり、順番がある。学ぶ過去があるということは、豊かな資産を有しているということであって、その資産をいかに流動化させるかによって、未来に向ける次の一歩の力強さが変わってくる。
本年は、NHKの大河ドラマに紫式部が取り上げられている。日本の香りに携わる者として、わが国の香文化にとって「源氏物語はバイブル」と標榜してきた私は、世の中の注目が多少なりとも王朝の麗しさに注がれることは良い機会だと捉えている。
千年昔の藤原時代、日本文化の独自性が開花したと考えている。それが今日に至るまで享受されてきた。ならばその千年昔に立ち返った時、その時点にとっての歴史や過去とは、どのようなことだったのだろうか。日本文化を考えるにあたって気になるポイント、光る君に至るまでを、いくつか列挙してみたい。
・梅は冬? 春?
私たちは、梅は早春と捉えている。春の花と考えていないだろうか。松や竹と共に「歳寒の三友」というように、本来の東アジアの概念においては、梅は冬の花だ。大陸では冬と認識されている梅を我が国では春と咀嚼しなおしている。
・奈良の建築
法隆寺や薬師寺の塔。誰が千年以上も立ち続けると考えていただろうか。でも現実に結果が出ている。どれほどに高度な技術がもたらされ、素直に学び挑戦したか。法隆寺の塔の五層の屋根は、何故に美しく開いているのだろう。何故に同じ比率で法起寺の三重塔があるのだろう。唐招提寺の金堂のあの美しい屋根を支える柱は、何故ギリシャの建築様式を反映しているのだろう。唐様摂取を志した人々の仕事の品質を知ることができる。
・文字文化
多くの漢字は、象形文字として生まれている。意味を持っているので表意文字とも言える。大陸からもたらされたそれらの文字は、真名と呼ばれた。それに対してその文字の音を利用して生み出されたのが、仮名という文字だ。カタカナと平仮名がある。仮の文字とされたこれらの文字は音だけを表す表音文字だ。この表音文字によって、紙の供給もままならなかった千年の昔に、世界史的にも例を見ない女流文学が花開いた。そしてそれらの小説や随筆が今も人々を魅了している。表意文字と表音文字を混在させて自己を表現できる文字文化を持ち合わせている私たちは、いったい何者なのか。
・古今和歌集
学校の教科書では、必ず、初めての勅撰和歌集として古今和歌集は紹介されている。私は「やまとうたしゅう」と読むようにしている。この国で初めて編纂されたやまとのうたのコレクション。それまでは教養ある人々にとって、唐様の歌こそが歌で、古くから口ずさまれてきたものは歌と認められていなかった。平安京における暮らしが始まってちょうど百年ほど経た900年頃の空気感、大きな機運の転換を教えてくれる。遣唐使の廃止も同じ時期。
・都市建設
海の向こうにある活力あふれる「都」を我が国にも建設しようと何度も挑戦が繰り返された。藤原京・平城京・長岡京と大きなものだけでも三度も挑戦があった。全て、何らかの失敗感があってやり直しを余儀なくされた結果、四度目の挑戦で、なんとなくみんなが納得する形が整ったのだと思う。平安京の誕生だ。平城京は、数万人の人々が集うには、水が足りなかったのであろう。平安京は、北東から南西へ、すべてのものを洗い流すだけの豊かな水が保障されていた。何度にもわたる都市建設の目的はすべて同じ。唐様の都の具現だった。ついにその達成感を得た人々は、唐様に対する違和感を感じ始め、和様化の活力へと繋がっている。
・顔のにおい
源氏物語「紅葉賀」で光源氏の麗しさはこの世のものとは思えないと表現されている。晩秋の風に庭の紅葉した木々の葉が次々に舞い、そこへ青海波を舞う若君の姿が輝いて美しい。冠に挿されたひと枝の紅葉も風や舞の動きに応じて枝だけとなり、光源氏の「顔のにおいにけおされたるここちして......」と表現されている。色白で透き通るかのような肌の美しい源氏が、冷たい風の中で一生懸命舞うことで頬の色が紅潮し、その赤みを帯びた麗しい姿に人々が見惚れている。においは、赤みを帯びたあたたかい色合いを表現している。鼻で感じる嗅覚情報ではなく目に映る視覚情報なのだ。魏志倭人伝に「倭の人は肌に丹を塗る。その丹は山に産する」という記述が知られている。古墳にも赤い丹はしばしば見受けられる。各地に伝わる丹生という地名。今日、私たちが鼻で感じる匂いは、視覚的な言葉でもあった。
・年表
学校の教科書で親しんできた年表は、どこに政があったかということだけしか意味を持っていない。四百年もの平安時代を一色に塗りつぶした年表では、社会気運の動きは読み取れない。人々の命の足跡を文化史として見つめ直すことで、歴史は面白さを教えてくれる。
思いつくまま、古代の我が島国の人々の暮らしを慮り列挙してみると、藤原時代の貴族文化がどのような背景を持った教養文化であったのか、そこへ至るまでにどのような流れがあったのか、考察するヒントにならないだろうか。私の担当する香り文化も、まさにこのような流れの中にあって、紫式部や清少納言などによって書き留められ、今日に伝わっているのだ。楽しくて仕方がない。
筆者
畑 正高(香老舗 松栄堂 前社長)
前社長が千年の都に生まれ育ち、薫香という伝統文化を生業にして、日頃考えることや学んだことを折に触れ書きつづったコラムです。