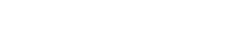- 旅の記憶
- 光る君に至るまで
- 表意と表音
- 志野宗信公五百年忌
- 香りってなに
- 中田浩二さんを悼む
- 寄り合うこと
- 蒼い香りと「令和」
- 30年という歳月
- 嗅覚と笑い
- 移り香
- 30年を迎えて
- 姉妹都市交流55周年 ボストンでコンチキチン
- 久蔵不朽 −久しく蔵して朽ちず−
- 異界と「丹の国」と
- SNS、五感、そして香り
- 生物多様性に生きる
- 匂いの発見
- 源氏千年紀に
- 祇園精舎での一会
- 宝船
- 背中に感じる巨大な息遣い
- らすとサムライ
- 伝統と革新の関係、その付き合い方
- データベースのすすめ
- 王朝の美学...消去法
- 3650
- 心清聞妙香
- 真新人類、待望論
- 香り...時空を越えて
- 香り...メディア??
- 君は船に乗るのか?
- Leotard
- 歴史のフィルター
- Huさん
- 常夏の街で
- 自然と芸術
- 赤いヤッケとリゾート開発
背中に感じる巨大な息遣い
「かおり風景」第20回掲載/平成17年
どんよりとした霞の中、機長の指差す方向はるか彼方、爪の引っかき傷かと見まがうばかりに滑走路を認めることができた。右向こうへ斜めに見えていたので、何とか私にも視認できたのだと思う。説明を受けるままに目を凝らして何度も尋ねなおし、なんとなく確信が持てた程度の実に頼りのないことであった。これから着陸をしようという滑走路は、あまりにも小さく消え入りそうな線でしかなく、自分が今直面している現実に理解が及ばなかった。
安全管理の厳しくなった今日では全く不可能なこととなってしまったようだが、かつての少しおおらかな時代には、子供連れの家族が操縦室に案内してもらったなどという楽しい土産話が聞けたものだ。航空会社のほうでも、機種ごとに準備された美しい写真カードに「ようこそ Flight No ○○○へ」などと書いたものを準備していて、訪問の記念に機長がサインを沿えて下さったりもした。私にも何度か幸せな体験がある。北米路線に搭乗したとき、わざわざ座席まで呼びに来てくださったので操縦室を訪問すると、暗闇の中に浮かび上がった計器類が実に美しかった。そして、目が慣れてきたときに驚いたのは、操縦席の窓の外に揺れ動く不思議な光のカーテンの存在だった。オーロラだった。とても静かに揺らめくその動きの不思議さと、近いのか遠いのか距離感がつかめなかったことが今も記憶に残っている。
水平飛行の間には許されていた操縦室の訪問も、離着陸時には許可されていなかった。それを押して、機長席の後ろに座らせていただいたことがある。ご迷惑がかからないように、航空会社や空港の名前は伏せておこう。機種はテクノジャンボだった。客室とは違い、この席では5点式のシートベルトで身を固める。これだけでも緊張感が違っていた。ほとんど意味の解らない計器類でも、見つめていると、機体の傾きの様子やどんどん下がっていく飛行高度の様子が理解できてくる。緊張と集中がとても心地好いのだが、前述のように、遥か遠くに見える滑走路は実に頼りない。小さな操縦室だけの世界に入り込んでいた自分の感覚からふと我に返ったとき、この空間の後方にあの大きな機体がぶら下がっているのだと気がついた。数百名の人々の命と共にこの小さな空間があるのだと意識したとき、思わず握った手の中に感じる汗が違っていた。徐々に目の前に迫ってくる滑走路が巨大な機体を受け止めるだけの大きさに迫力を増し、後輪から、そして機首を下ろし前輪も着地。始まった逆噴射の反動の中で大きく安堵したことが、実に鮮明な記憶として残っている。
昨今、あの操縦室での一度だけの体験をふと思い出す。自らの背後に多くの人々の息遣いを感じるという感覚は、一つの社会そのものだと思うようになってきた。社内や地域社会などで、先輩世代が引退していかれる。ふと意識してみると、いつの間にか自分の前にはほとんど人が居られず、自分の背中を信じて日常を歩む多くの若き世代達の足音が響いている。気持ちが負けそうになってしまうときもあるけれど、そのとき自分の中に呼び戻すべき空気は、あの着陸態勢に入った操縦室の責任感と自信だと思えるようになってきた。素晴らしい体験に感謝を覚えている。
筆者
畑 正高(香老舗 松栄堂 前社長)
前社長が千年の都に生まれ育ち、薫香という伝統文化を生業にして、日頃考えることや学んだことを折に触れ書きつづったコラムです。