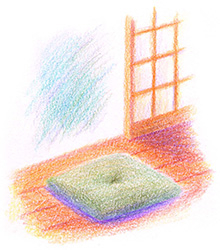メニュー
入賞作品の発表
第31回 「香・大賞」
金賞
『 同じ匂いを知る人 』
伊藤 優花(いとう ゆか)
- 23歳
- 会社員
- 愛知県
「ふゆの匂いがするよ、お母さん」
随分詩的な事を言うのね、そこどいて、洗濯物干すから……。洗濯物の山と母が鼻先を通り過ぎ、冬の匂いは一瞬にしてありふれた柔軟剤の匂いへと変わってしまった。結露のはったガラスに映るやせっぽっちで引っ込み思案の少女、それが幼い頃の私だった。
父のいない我が家で父親代わりをしてくれた祖父は、祖母が病に倒れてからは、一人自分の和室に籠もることが多くなっていった。折しも思春期を迎えようとしていた私は、部活や友人関係、進路や定期テストなど自分の面倒事だけで毎日手一杯で、無口な祖父が前よりもっと無口になったことに気が付く余裕はなかった。いや、心のどこかでは気が付いていたのかもしれない。それでも何もしなかったことが私の罪の名前だ。
やがて祖父は全てを忘れていった。自分の生年月日もかつての勤め先も、祖父にとっては必要のないものになったようだった。だからきっと神様は祖父の記憶からそれらを消してしまったのだろう。
街にその冬最初の寒波が訪れた日。寒いのに障子を開け放したまま、定位置である座布団の上に小さく座っている祖父に、私は
「窓を閉めるよ、おじいちゃん」
と声をかけた。聞いているのかいないのか、祖父は入れ歯の入っていない口をもぐもぐさせた。
「ふゆの匂いが、するなぁ」
背中越しに、ふいにぽつりと聞こえた祖父の声に、私は一人になってから静かに泣いた。この人が私を忘れたって、私たちは家族だ。同じふゆの匂いを嗅いだ、家族だ。
次の冬を待たずに祖父は旅立った。享年91の大往生だった。
天国のおじいちゃん、今年も冬が来ました。そっちでも同じ冬の匂い、していますか?