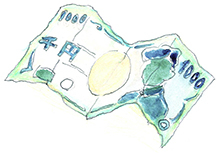メニュー
入賞作品の発表
第32回 「香・大賞」
銀賞
『 しわくちゃの千円札 』
森上 佳奈(もりかみ かな)
- 22歳
- 大学生
- 静岡県
百貨店の営業時間が終わると、店員の私はその日の売り上げを入金機に入れる。時々、入金機に読み取ってもらえないお札がある。今日読み取られなかったのは、しわくちゃの千円札だ。店員の皆がこれを厄介者扱いした。しかし私は、しわくちゃの千円札が愛おしかった。私にとってそれは、曽祖父なのだ。
彼に会うのは、年に一度祖母の家に行く時ぐらいであった。幼かった当時の私から見て、彼はどうやら恐れられているようであった。普段は奥の和室に閉じこもったまま出て来ない。とても気を遣われていて、私達家族に振る舞うお吸い物についても、一人一つの玉子を入れていいかどうか、私の祖母は彼に許可を取りに行っていた。その日、私達家族が帰ろうと玄関で靴を履いていると奥から彼が出て来た。私の前に立つと無言で右手をこちらに伸ばしていた。母に肩をつつかれ、初めて彼が何かを差し出しているのに気付く。それはしわくちゃの千円札だった。ありがとう、緊張した私はなんとそれすら言えなかったのだ。100歳近い彼が細い腕を伸ばす姿を思い返しては何も言えなかった自分を責めて泣いた。彼に会ったのはそれが最後だったのだ。
今考えれば戦時中を生き抜いた曽祖父にとって、玉子は贅沢品だ。千円だって幼い子供に与える額でなかったかもしれない。ぶっきらぼうなお小遣いの渡し方は、曽祖父の照れくささからくるものだったのだろう。
私はずっとその千円札を使わずに袋に入れてある。袋に入れているのは、お札にまで染み付いた彼の和室の臭いが抜けないようにするためだ。それは線香と彼の体臭とが混ざったような不思議な香りである。18年経った現在、さすがにその香りは残っていない。でも私はその袋を開いた時、あるいは仕事場でしわくちゃの千円札に出会った時、いつだって彼の香りを感じる。その度に私はあの時言えなかった『ひいおじいちゃん、ありがとう』を心の中で繰り返し伝えている。