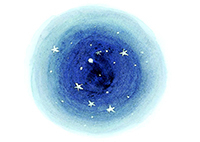メニュー
入賞作品の発表
第34回 「香・大賞」
銅賞
『 わたしたちのいくところ 』
やまろ まさし
- 59歳
- 翻訳者
- 神奈川県
平成最後の夏は猛暑と水害の夏だった。
うちの実家も少しやられた。祖父母が眠る墓で水が出た。寺域近くの沢があふれて、境内を洗っていったのだ。
「すまないけど、ちょっと帰っといで」
母からSOSが来た。老母一人に後始末させるわけにもいかない。やりくりをつけて二日の休みを取った。すぐ寺に向かった。住職は泥の層を指して、これでも被害は軽微なほうで「テレビも来やしない」と笑った。
とはいえ大仕事だ。沢に近い墓は流され、香炉など小ぶりの石器はどれがどこの家のかわからない。うちのは沢から遠く、水の当たりは弱かったそうだが、それでも墓石はズレていた。ぽっかり黒い口を開けた唐櫃(カロート)をのぞくと、骨壺のふたは外れ、水が溜まっていた。炉の灰を水に漬けたような、どうにもほめようのない困った色をしていた。
「こりゃ、二人とも溶け合っちまったな。どうするよ? 母さん」
「いいんじゃないの。夫婦なんだし」
末枯(すが)れたことを言う。だがその通りだ。
「母さんも、こうなるかい?」
「フン、お前もね」
言うと思った。祖父母とも、ヘソ曲がりのこの母とも、うまくすれば子供らとも、私たちはいつか溶けて混じって一つになって、それからはこの星の一部だ。
「あいつらにも見せてやりゃよかったな」
「およしよ。怖がるんじゃないかい」
「ないない。もう社会人だよ」
「そうかい。もうそんなかい」
「そうだよ。もうそんなだよ」
線香を焚いた。それだけで地下も地上も一息ついた景色になれる不思議。まるで一仕事終えて薫(くゆ)らす煙草の一服にも見えてくる。
「線香も《喫(きっ)する》と言うのかな?」
「さあね。自分で調べな──」
これだ。知ってるくせに。翌日子どもらも助っ人に来た。夕刻、墓は元に復した。