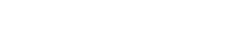- 表意と表音
- 志野宗信公五百年忌
- 香りってなに
- 中田浩二さんを悼む
- 寄り合うこと
- 蒼い香りと「令和」
- 30年という歳月
- 嗅覚と笑い
- 移り香
- 30年を迎えて
- 姉妹都市交流55周年 ボストンでコンチキチン
- 久蔵不朽 −久しく蔵して朽ちず−
- 異界と「丹の国」と
- SNS、五感、そして香り
- 生物多様性に生きる
- 匂いの発見
- 源氏千年紀に
- 祇園精舎での一会
- 宝船
- 背中に感じる巨大な息遣い
- らすとサムライ
- 伝統と革新の関係、その付き合い方
- データベースのすすめ
- 王朝の美学...消去法
- 3650
- 心清聞妙香
- 真新人類、待望論
- 香り...時空を越えて
- 香り...メディア??
- 君は船に乗るのか?
- Leotard
- 歴史のフィルター
- Huさん
- 常夏の街で
- 自然と芸術
- 赤いヤッケとリゾート開発
心清聞妙香
「かおり風景」第15回掲載/平成12年
中国唐朝の詩人・杜甫の「大雲寺賛公房四首」という詩に、この「心を清らかにして、妙なる香りを聞く」という一節があります。夜陰の静けさの中、灯火の明かりに神秘的な影が浮かび、眠ることを忘れてしまった。さめざめと冴えゆく心の深淵を照らし出すかのように、香の妙なる香りが琴線を振るわせ余韻を残す。情景としてはこのようなものでしょうか。嗅覚をもって感じ取る香りに対して、「匂う」や「嗅ぐ」また「香る」でもない、この「香を聞く」という表現は、1200年の時を経て今も偉大な詩人の豊かな感性の深さを充分に語りかけてくれています。
インド北部に点在する「八大佛蹟」。その一つ、ヴァイシャーリでは、乾燥した大地に今も大きなストゥーパ(仏塔)と有名なアショカ王の石柱が往時の趣を伝え、遠来の訪問客を迎えてくれています。この遺蹟は、在家信者として活躍した維摩居士とその「維摩経」の故郷として知られています。「香を聞く」という表現を考えるとき、この「維摩経」に説かれた「香積佛品(こうしゃくぶっぽん)」の教えに、そのルーツを見付けることが出来るのです。
天上高くはるか遠い仏国土に「衆香国」と呼ばれる世界があるそうです。維摩によって使わされた化菩薩がこの仏土を訪問し「香食」を頂いて帰るとき、多くの天上の菩薩たちが娑婆世界を尋ねてみようと維摩の家へ下ってまいりました。これによって仏国土の菩薩たちと、娑婆世界の維摩居士との間で情報交換が始まりました。話しを聞いてみると、「衆香国」には香積如来という仏様がおられ、文字を用いて法を説かれるのではなく、妙なる香りによってすべての者が戒律のなかですばらしい三昧を得られるように導かれると言う事でした。それに比してこの娑婆においては、あまりにも強い煩悩に支配された私達には、釈迦牟尼仏は強烈な言葉を持って法を説かれ衆生の魂を救わんとされてきたのです。
この事から、いまや涅槃をされた釈迦牟尼仏の教えに対し「法の声」として耳を傾ける事しか方法の無かった衆生にとって、妙なる香の香りに身も心も委ねる事は、「衆香国」の菩薩達にあやかる一つの可能性となったのです。法を聞かせていただくのと同じように香も聞くべきものとして捉えられるようになりました。
嗅覚に対する刺激として私達が出会う香の香りに対し、単に鼻先で感じ未熟な経験値の中で軽薄な判断に終わってしまうのではなく、深く魂を震わせるように接し、香そのものが天然の素材であり人知によって創造することのできない天授の世界であると気付いた時に、自ずと自然に対する畏怖を感じざるを得なくなってしまうのです。
500年ほど前にわが国において確立された「香道」の世界。やわらかな炭団の熱によって天然の香木を優しく温め、立ち上る芳香に静かに魂を傾けるこの芸道において、この「聞香(もんこう)」という表現がいかにも相応しく用いられます。そして、この美しく深みのある「香を聞く」という表現が、今日「香りの時代」を迎えたと言われる日本において、また再び見つめなおされつつあるのです。絶対的な存在として自然界と真摯に対面するこの姿勢は、視覚や聴覚に依存をしすぎてきた20世紀人にとって、「地球との共生」を実践しなければならない21世紀に、生まれ変わるきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。
筆者
畑 正高(香老舗 松栄堂 社長)
千年の都に生まれ育ち、薫香という伝統文化を生業にして、日頃考えることや学んだことを折に触れ書きつづっています。この国に暮らすことの素晴らしさ、世界の中に生かされていることのありがたさ…お気付きのことがありましたら、お聞かせください。